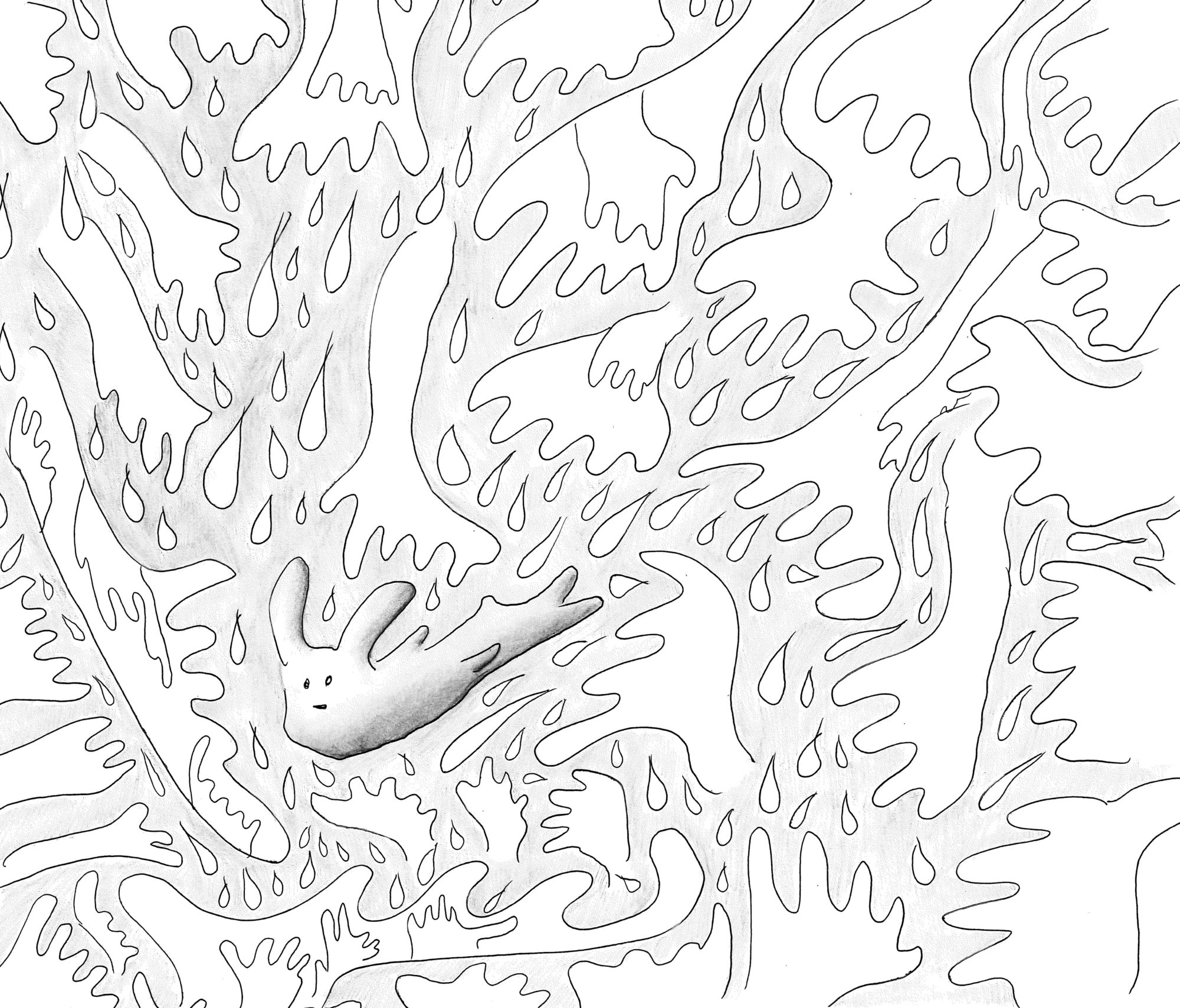父の物語、あるいは——村上春樹クロニクル
深沢レナ
村上春樹はいつから僕たちに嘘をつかなくなったのだろう?
2015年、村上春樹が小説家として自身の歩みを綴った『職業としての小説家』というエッセイのようなものが発売された。多くの彼のファンと同様、近年の作品はあまり好きになれないけれどもとりあえず彼の新刊が出ればすべて手に取ることにしている僕は、発売日の数日後に紀伊国屋でそれを買って読み出したのだが、正直言ってそこに書かれている言葉のあまりの素直さにいささか驚きを感ぜずにはいられなかった。そこで彼はあまりにも普通に、せきららに、自分の歩んできた道や小説家のあり方についての理念を語っていた。その上そこに書かれている内容には真新しいものはほとんど見受けられなかった。それらは彼が今までに出したエッセイや、読者とのメールのやりとりの中で繰り返し言い続けていることがほとんどだった。その一方でそこにはもうかつてのように、油断しているとすぐに隠し事をしたり、くだらない冗談を言ったり、嘘を言って読者を騙していた頃の彼の軽やかさはなく、新しい書き手のために真面目に話をしなくてはならないという重厚な責任感が滲みでていた。おそらく村上春樹という作家はあまりにも大きな存在になりすぎてしまったのだ。僕は彼から失われたしまった何かを想っていささか悲しい気持ちになり、最後まで読み通すことなくそのまま本を閉じた。
村上春樹が神戸の古本屋でアメリカの作家たちのペーパーバックを買っていたのとおおよそ同じように、僕も中学の頃から学校が終わるといつも駅前の古本屋に寄って100円とか200円のタグを貼られた村上春樹の本を買い漁ったものだった。最初に読んだのはたしか『羊をめぐる冒険』だったと思う。別に理解なんてしていなかった。北海道の歴史に関する記述ははっきりいって退屈だったし、羊男なるものが意味するところもよくわからなかったけれど、不思議と彼の文章を読んでいるといつもより息がすっと抜けるような気がした。それは学校で読まされていた三島や太宰や芥川の文章とは明らかに違う種類の言葉だった。コテコテの装飾もなく、ウジウジとした自意識もなく、小説家につきものの読んでいるこちらを見下してくるような選民意識もなかった。なによりそれまで日本の小説に感じていたなんとなくベタっとした感触がまったく感じられなかった。そういう風通しのいい小説を読むのは僕には初めてのことで、そんなタイプの文章が存在するということは当時僕にとってとても大きな発見だったのだ。それから僕は『風の歌を聴け』を読み、『1973年のピンボール』を読み、村上朝日堂シリーズを読み、高校にあがるときには気づけばすでに村上春樹という小説家の世界にどっぷりとはまりこんでいた。
あくまで僕にとってはということだけれど、その頃の村上春樹は思春期の少年にとって本当に必要なこと——次に何を読むべきか——を教えてくれる貴重な、かつ唯一の存在だった。彼の小説を読み終えると今度は彼の翻訳したレイモンド・カーヴァーやスコット・F・フィッツジェラルドやティム・オブライエンといった作家の小説を読み、それもだいたい読み終えると彼がエッセイの中で言及していた本を片っ端から読んでいった。彼は特別親切なわけでも面倒見がいいわけでもなかったが、彼の後ろになんとなくついていっていれば、たどり着いた先にはちゃんと面白いものがあった。彼は言うなれば、ちょっと年のはなれたいとこのような存在だったのだ。「めくらやなぎと眠る女」のなかで、耳の悪い年下のいとことバスに乗って新しい病院まで連れて行ってくれた「僕」のように。
だからこそ2009年に『1Q84』が発売される前のある種のお祭り騒ぎのようなものに僕は戸惑いを隠せなかった。僕はその頃にはもう大学生になっていたのだが、それでもときどき本棚から彼の本を取り出しては読み返したりしていた。『1Q84』の発売日前日には本屋の前に行列ができていて、深夜から彼の本を求めて並ぶ人々の様子がTV中継されていた。いざ発売されてみると、あらゆる本屋が彼の本をジェンガのようにうず高く積み上げ、いたるところでリトル・ピープルやふかえりのことが話題となり、すぐさま「『1Q84』解説本」が出回り、ニュース番組ではその小説世界の図解すら行われていた。月が二つあるやら、さきがけはオウム真理教であるとかなんやら。
思えばその頃が「村上春樹現象」の最盛期だったのだと思うけれど、僕はそういった村上春樹をとりまく熱狂のモードに辟易せざるをえなかった。いったいこれはなんなんだ。年上のいとこのような存在だった彼は、もう僕にとって親密な存在ではなくなっていた。それに加えて実際に自分でも『1Q84』という小説を読んでみて、その物語や人物設定になんとなく違和感を抱くこととなった。なにより文章があまりにも説明的でわかりやすすぎた。かつて村上春樹の小説の中にあった余裕や、言葉への不信感といったものはどこにいってしまったのだろう。僕の中に生まれたそれらの違和感は、次の年に続編が出版されたときによりくっきりと明確に形をもつようになった。青豆だとか天吾だとかいった名前や泥臭くて汗臭い設定は、好きではないけれどもまあ許せなくはない。しかし主人公の一人である青豆が、死ぬことを中断して生きることを選択するという話の展開にはどうしても無理があるように思えてならなかったのだ。そこには村上春樹自身の責任感がうまく馴染めずに残っているような、異物のごつごつとした感触があった。その存在は、作品がどことなく不完全であるような印象を僕に抱かせた。僕は『1Q84』を最後まで読み通すことなく本棚の奥にしまった。そして思った。結局のところ、村上春樹という作家は所詮僕にとって通過していくだけの存在だったのかもしれない、と。
それからも新刊が出れば一応読みはするものの、その度に僕は彼の小説世界にあったはずのものの幻影を思い起こすばかりだった。トニー滝谷が残された妻の服を眺めてもかつて存在したものがあとに残していった欠落感を触知するだけだったように。だから今こうやって村上春樹という作家について何かしらの文章を書く機会を与えられたとき、僕は最初彼の初期の作品について書くつもりだった。そうして僕は彼の作品をクロノロジカルに読み進めていった。彼の昔の作品をゆっくりと読み直すという行為はとても幸福な体験で、それは僕にひそやかに行われる親密な同窓会を思わせた。そこには変わることなく鼠がいて、ジェイがいて、小指のない女の子がいた。208と209という双子がいて、配電盤のお葬式があった。猫の名前に関するどうでもいいような会話がなされ、命をかけた大冒険にはどこかしらのんびりとした時間が流れていた。〈アメリカの鱒釣り〉の日本版のような〈貧乏なおばさん〉が背中にはりつき、4月のある晴れた朝には100パーセントの女の子とすれ違った。そしてそこには突撃隊と彼のラジオ体操の話をする「僕」がいて、それを聞いてくすくすと小さく笑う直子がいた。
『ノルウェイの森』まで読み終えて本を閉じ、赤と緑のあざやかな装幀を見つめながら僕は何をするともなくただぼんやりと考えこんでいた。それらの本の中には軽やかなユーモアがあり、心を震わせる何かへの抑えがたい憧憬があり、結局のところ僕たちにできることは何もないのだという静かな諦念があった。そういったものたちがもうすでに失われてしまったのだと思うと、やはり僕は哀しい気持ちになった。
けれどもその一方で——以前読んだときにはそんなことはなかったのだが——それらの作品には明らかに足りていないと感じさせる何かがあった。もちろん小説は小説としてどれも素晴らしい出来だったし、軽い表面を装いながらも人間の病というものの深くまで潜り込む深淵さを兼ね備えていた。今でもこれらの小説を読むと物理的に心を突き動かされたし、心の震えを感じさせられたのは確かだ。しかしそれはそれとして、これらの小説たちにはあまりにも救いがなさすぎ、あまりにも「完成」されすぎていた。それは言うなれば「閉ざされた完全さ」だった。美しく完成されすぎてしまった直子の体が結局は死以外に行き着くところをもたなかったのと同じように、そこにある完全な小説たちは、完全であるがゆえに行き場を失っているように僕には思えた。
それから僕はこのように考えるようになった。『1Q84』に感じたある種の不完全さというものは、作者の過失によって生じたものではなく意図的に志向されたものなのではないだろうか。村上春樹という作家は、その不完全な作品を見せることでしか語ることのできない何かを僕たちに語っているのではないのだろうか。そしてその何かとはまさに、僕が最初その作品に余計な異物ものとして感じた「責任」というものではないだろうか。もしかしたら彼は、ごつごつとした「責任感」をあえて入れ込むことで、「大いなる不完全さ」ともいうべきものの形をつくりあげているのではないか。
*
村上春樹の中にはっきりと「責任」というものの萌芽が芽生え始めたのは『ねじまき鳥クロニクル』の頃だった。
1991年1月17日、湾岸戦争が始まった。クウェートからのイラク軍の撤退を要求するジョージ・ブッシュ大統領(父親の方)が空軍にバグダッド空爆を指示し、本格的な戦争が開始されたのだ。ニュージャージー州にあるプリンストン大学に滞在する予定だった村上春樹は、その日ビザを取るために大使館に向かうタクシーの車内でそのニュースを耳にした。
不安を抱えながらも到着したアメリカには「準戦時体制」の切迫した空気が漂っていた。プリンストンの街のいたるところに巻かれた従軍兵士たちを讃える黄色いリボン。テレビのニュースで繰り返し繰り返し映し出されるバグダッドを攻撃する空軍機から撮られた画像。兵器の無駄のない美しさと若い兵士たちのクリーンな顔つき。エチゾチックな砂漠の風景と宙に翻る星条旗。暴力と暴力のぶつかりあい、英雄と悪漢。そして街の人々の漂わせる高揚感……。戦争とはそういうものだ。
次第に戦争が大掛かりになるにつれ、村上春樹はどこかに顔を出すたびに、その戦争に対する日本の貢献についての疑問なり追求なりに直面することとなった。これだけ多くの国が対イラクの攻撃に参加しているのに、どうして圧倒的な経済力を誇る日本が何もしないでいるのか? しかしその問いに対してどんなに論理を並べ立てても、武力の行使を放棄するという憲法を掲げながら自国軍隊を持っている日本の「ねじれ」を説明することはできない。それに何といっても当時の日本の経済力は圧倒的に強かったのだ。リセッションのまっただ中にあったアメリカではジャパン・バッシングが蔓延していた。にもかかわらず日本人は自分たちに不快感を向けられても、その経済力に見合うだけの、国家としての、あるいは文化環境としての意思や方向性を、世界に対してほとんどまったく提示することができずにいた。それを提示できないことに対する危機感は日本人の側にはほとんど見受けられず、そういう状況に対して彼はやはり暗澹たる気持ちにならざるをえなかった。
そして1991年12月7日、太平洋戦争が始まって50年目の記念日で、一般的な反日感情はピークに達した。彼は妻とともにその日一日家に籠り、一切外に出ることはなかった。プリンストンという穏やかな大学街にあってもあたりの空気はぴりぴりとした感触をまとっていた。戦後生まれの人間だからといって「私は関係ありません」と突き放せるような空気はそこにはなかった。多かれ少なかれ日本人として、自分たちの父親たちが戦争中になしたことについて、歴史的な責任を負い続け、自分たちのうちにそうした記憶を共有物として保存しておかなくてはならない。そう実感させられることになった村上春樹は、五十年前に起こった歴史的事件の中に自分が否応なく含まれるのを感じとる。そうやって時間と空間を超えて歴史とつながるような当時の感覚が、1939年のモンゴル・満州国境と現在の東京を行き来する不条理な物語を形作ることとなったわけだ。
『ねじまき鳥クロニクル』は妻が突然行方不明になり、主人公である夫の岡田亨が彼女の行方を捜索する物語である。所帯をもたない個人が主人公であることが多かった村上作品ではじめて夫婦というものが扱われたのだった。岡田亨はたくさんの登場人物にさまざまな形でコミットメントを迫られる。電話をかけてくる謎の女、近所に住む十六歳の少女笠原メイ、霊媒師の加納マルタと加納クレタ、占い師・本田さんの形見分けをしにきた間宮中尉。多種多様な人物たちが岡田亨のところにやってくる中で、ただ一人彼が本当にコミットしたいと願う妻のクミコだけが逃げていく。だが岡田亨は、あくまで彼女自身の言葉を聴くことを希求し、自ら積極的に彼女を探してそのために闘いもする。彼には「何があっても妻を探しだす」という一貫した強い意志がある。
岡田亨はやってくる人々に各々の体験談を聴かされる。謎の女はしつこく電話をかけ、笠原メイは死のかたまりみたいなものへの魅惑を語り、加納クレタはいかにして自分が綿谷ノボルに汚されたのかを語り、間宮中尉は五十年前ノモンハンで起こった事件のことについて語る。この小説では一人称が用いられながらも、主人公の視点から離れたところにあるありとあらゆる登場人物の声がつめこまれることによって、水平的に流れる時間に歴史を縦糸にして垂直な流れを取り入れるという、その後の村上作品にお馴染みの手法が本格的に試みられることになったのだ。
それまでも村上春樹の小説には初期の頃から「聴く」という行為やそれにまつわるものがよく描かれていた。デビュー作『風の歌を聴け』(1979年)にはじまり、「見知らぬ土地の話を聞くのが病的に好きだった」『1973年のピンボール』(1980年)、『羊をめぐる冒険』(1982年)で共に旅をするのは「耳」のモデルをしている女の子であり、『世界の終りハードボイルド・ワンダーランド』(1985年)では老博士によって音が抜かれる。『回転木馬のデッド・ヒート』(1985年)は「僕」による「聞き書き」という形式を利用して書かれた短編集だ。そして『ノルウェイの森』(1987年)では緑や直子やレイコさん、『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)では五反田君といった、多かれ少なかれ心に病を負った人々の話を聴く「僕」という人物が主人公であった。ここに見えてくるのは「聴く」男たちの系譜だ。
不満を抱くこともなく、人々の話をひたすら聴くという彼らの努力にもかかわらず、彼らが求めるものは、闇のなかをとぶ蛍のようにはかなく消えてしまう。そんな彼らに対し『羊をめぐる冒険』では、もうすでに死んでしまった「鼠」が「僕」に重要な指摘をする。
「キー・ポイントは弱さなんだ」と鼠は言った。「全てはそこから始まってるんだ。きっとその弱さを君は理解できないよ」
「人はみんな弱い」
「一般論だよ」と言って鼠は何度か指を鳴らした。「一般論をいくら並べても人はどこにも行けない。俺は今とても個人的な話をしてるんだ」
僕は黙った。
(『羊をめぐる冒険(下)』)
何もかもを一般論にしてしまう主人公たちは個別の痛みというものを理解できない。あらゆる物事を数値化し、双子や猫に名前をつけることなく、意味を還元して記号にしてしまおうとする彼らは、たえまなく暗闇にひきずりこまれていく人間の個人的な弱さの重みを受け入れられないのだ。そして「一般論」として片付けられて出口を失った鼠や直子や五反田君は死に、周囲の人物を無自覚に傷つける「僕」は大切な者を失い続ける。その構図は『ねじまき鳥クロニクル』においても変わらない。鼠のセリフは「あなたの中には何か致命的な死角があるのよ」という謎の女の言葉となって反復される。
『ねじまき鳥クロニクル』は今では第三部までのひとまとまりの作品として認識されているが、もともとは前作『国境の南、太陽の西』の単行本刊行と時を同じくして、第一部1992年から1993年まで連載されたあと、1994年に第一部、第二部が同時刊行された。当初、この作品は未完と断られることなく刊行されたため完成作として受け取られたのだが、1995年に第三部が出て、最終的には三部構成で完成するという異例の形態をとった。
ではその間にはなにがあったのか? 第二部と第三部が出される間に村上春樹に起こったこと、それは、ユング派の心理学者河合隼雄との出会いだった。河合隼雄は、上下関係を好まない村上春樹がその後唯一「先生」と敬称をつけて呼んでいる稀有な存在であるが、1994年に会って話をした時のことを村上春樹はこう述べている。
河合隼雄さんとはアメリカに住んでいるときに、何度かお話をする機会を得た。(中略)僕はその当時ちょうど『ねじまき鳥クロニクル』という大変に長い長編小説を書いているところで、物語の深い霧の中にほとんどすっぽりと浸っているような状態だった。自分の物語が自分を含めたまま、どこかに向けて確実に進んでいくのはわかるのだけれど、その「どこに」というのがさっぱりつかめない。あらゆるものが複雑に入り組んでいて、簡単には仕分けのできない状態にあった。おまけに現実と物語とがところどころで薄暗く入り乱れていた。三年くらい片づけをしていない混んだ押入を想像していただければ近いかと思う。
でも、そういうときに河合さんと向かい合っていろんな話をしていると(小説のことはほとんど話さなかったのだけれど)、頭の中のむずむずがほぐれていくような不思議な優しい感覚があった。「癒し」というと大げさかもしれないけれど、息がすっと抜けた。
(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
村上春樹は河合隼雄に話を聴いてもらうことによって(その対談は河合隼雄『こころの声を聴く』に収録されている)、それまで現代文学において重要な命題だと見なされていなかった「物語」というものに対する物理的な実感を共有することになる。そこで彼の言わんとする「物語」の概念の総体を説明なしで総合的に受け入れてもらえたことは彼にとって大きな励ましとなり、彼の中にある漠然としたビジョンが明確な図を結ぶこととなったのだ。
『ねじまき鳥クロニクル』第二部までの閉じられた物語は、第三部がつくられることによって開かれ、岡田亨は赤坂ナツメグという女性の後継者として新たに「仮縫い」という仕事を始める。「仮縫い」はさまざまな人の話を聞くことのアナロジーとして読めるが、村上春樹自身が河合隼雄に仮縫いされ、「聴く」力を継承されたことによって、一般論に収集してしまうがゆえに「聴く」ことに失敗する物語であった初期から、人々の個別の話に耳を傾ける後期へと「聴く力」の意味の大きな転換がなされる。その結果、なくなった何かを探し求めながらも失うだけだった彼の作品に「救い」という新しい道が開けたのである。
そして第三部を書き上げてアメリカから日本へと帰国した村上春樹は、地下鉄サリン事件の60人を超える数の被害者に会い、ロング・インタビューをおこない、詳しい聞き書きという形で一冊の本にまとめる。それが1997年の『アンダーグラウンド』であり、次の年にはその続編ともいうべき『約束された場所で』に取り掛かる。後者はオウム真理教信者及び元信者に取材したものだ。この二つの「非フィクション」の中で、彼はもはや「僕」であることをやめ、「筆者」もしくは「私」という形で息を潜め徹底して人の話を聞くことにつとめている。そもそもインタビューという作業は、自分は無色透明な聞き手となって、個別の人々——それも普通の人々——の話に耳をすませ、彼らがどうやって生きてきたのかというそれぞれの物語を自分の中に受け入れ文章化する作業だ。一言で言うなら、それは三人称の作業なのだ。村上春樹は証言者たちの語りという物語をひとつひとつ身をもってくぐり抜け、そしてそのミクロコスモスを重ね合わせることによって、総合的なあるがままのひとつの世界を作り上げたわけだが、それはまさしく彼の敬愛するディケンズやドストエフスキーらの総合小説の形へとつながっていくこととなったのだった。
その後彼は1999年に中編『スプートニクの恋人』で従来の文体の見納めをすませると、連作短編集『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)にて、阪神大震災により何らかの影響を受けた人々の話を全面的な三人称として描く。短いものなら三人称で書けるという確信を得たのち、それを長い作品にもっていくという課題を長編『海辺のカフカ』(2002年)で実践する。ここでは一人称と三人称が章ごとに交代で出てくるという新しい構成を試みられているが、何よりも、主人公がはじめて15歳という年齢にまで引き下げられたのだった。2004年には中編『アフターダーク』にてカメラアイを用いて現代の世界を描いたあと、しばらく新作が心待ちにされていたが、ついに、7年ぶりの長編『1Q84』(2009年)において、完全なる三人称の総合小説——より客観性、多様性をもった集合的責任を著者が負うマクロなコスモス——が完成した。
2013年には、東日本大震災後に書かれた初の長編である『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』が出版された。主人公のつくるが大人になってから、かつての級友たち一人一人に話を聴きにいく物語だ。そしてつくるが唯一強い思いを抱いているガールフレンドを手に入れるために、正面からちゃんと向き合って話を聴こうと決意するところで物語は閉じられている。
*
2009年2月「エルサレム賞」を受賞した際、村上春樹はイスラエルに赴き、「壁と卵」というスピーチを行った。その時僕はちょうどニュースでその様子を見て驚いてしまったのだけれど(当時の危うい情勢の中わざわざ赴いて講演をするという彼の積極性にももちろん驚いたが)、公式の場で自分の家族についてふれることのなかった村上春樹が、そこでおそらくはじめて自身の父との関係性について話したのだった。「壁と卵」というメタファーと同時に(それは多くの人を感動させたと同時に多くの人を腹立たせたようだ)、彼が父親から日中戦争の記憶を引き継いでいたことを明らかにしたということは世間で大きな話題を呼んだ。それもそのはずだ。彼は自分自身の親について語るのを好まず、インタビューで父の話を聞かれてもあとからインタビュアーに電話をかけて削除してくれと頼むほどだったのだから。
しばしば指摘されていることではあるけれど、彼は初期作品の中で父なるものを描くことがなかった。主人公たちは誰にも支配されることなくどこにも属さない個人として設定されていた。家族もほとんど描かれることなく、描かれるとすれば横の関係が圧倒的に多かった。そんな「父の欠如」というものがひとつの特徴であった彼の作品に、やがて父の姿がぽつぽつと描かれるようになる。最初は『神の子どもたちはみな踊る』、それから『海辺のカフカ』や『1Q84』では父の相克や父殺しというテーマが描きだされ、それと同時に『海辺のカフカ』では年長者たちが少年のカフカに何か大事なものを引き渡していく様子が、『1Q84』では青豆と天吾が親となる予兆が示される。現在の段階で最新の長編『騎士団長殺し』(2017年)では、父になった「私」が自身の娘を、TVで放映される津波の光景から守る様子が印象的だった。
僕は思うのだけれど、そういった横から縦の関係性へという流れの中で、村上春樹という作家自身も「父」となっていったと言えるのではないだろうか。
『1Q84』の執筆中に、彼は実の父だけでなく、精神的な父ともいうべき河合隼雄も亡くしている。そして実の父から引き継いだ「戦争の記憶の遺産」、河合隼雄から「聴く力」を引き渡された彼は、自分自身も「父」になることで彼らから引き継いだものを次の世代に引き渡そうとしているのではないだろうか。かつてから『若い読者のための短編小説案内』(1997年)を出版したり、ウェブサイトではまるでカウンセラーさながら、読者からの何千何万といったメールをすべて読んで出来る限り返事をしていた彼だが、『職業としての小説家』という、まあ言ってみれば指南書みたいなものを書くことで、真剣に次世代の作家のために自分の「技」を伝授しようとし始めたのかもしれない。そう思って棚の奥にしまってあった本を取り出して、もう一度そのモノクロ写真の表紙を見たとき、そこにあるのはもはや涼しい顔をして軽妙洒脱な冗談を言っていた都会的な青年の姿ではなく、僕たちに向かってまっすぐ目を向ける「父親」の姿だ。
この国はよくなるのだという希望があとかたもなく崩れ去ってから生まれてきた僕たちは、今や自分たちの足元の地面が堅くて不動のものだとは信じていない。四方を海に囲まれたこの国のなかでどこにも行けないという無力感を抱えて生きるというのは、とめどなく回転を続けるメリー・ゴーラウンドに乗っているようなものだ。そんな僕たちが仮そめの救いを求めて小さな閉じた世界へと入ってしまわないように、地下のくらいところから手をのばして僕たちをとらえようとするやみくろに引きずり込まれないように、僕たちがその暗闇に対して正面から向き合うことを恐れて羊に魂を奪われないように、とにかく「悪しき物語」に対抗して「良き物語」をつくるのだ、と村上春樹は東京の地下でかえるくんの助太刀もなく、たった一人闘おうとする。
正直なところ僕には、驀進してくる機関車に立ち向かおうとするような彼の姿は無謀としか思えない。–だって所詮は小説家でしかないのだ。毎日朝4時に起きて執筆し、午後には十キロ以上走り、それから翻訳をして、食事に留意し、飲酒を適度に控え、夜9時には寝る。機械的な反復を日々続け、誰にでもわかるような容易い言葉で誰にもわからないような道理を説明しようと言葉を紡ぎ続ける。そうやって一生懸命何かと闘っている彼の姿を見ていると、変な話だけれども、僕まで一緒になってだらだら汗をかいてしまう。何かを相手に真剣にとっくみあっている彼を見ていると逆に見ているこっちが苦しくなってくるのかもしれない。笠原メイならこう言うだろう。かわいそうなねじまき鳥さん。
けれどもそんなほとんど勝ち目がないような状況で、わざわざ真っ暗なカビ臭い井戸の中に降りていき、自分も傷だらけになって同じく傷だらけの者たちを救おうとする村上春樹という作家の「大いなる不完全さ」の世界が、彼の全作品をもう一度壁抜けしてきた今の僕には、不完全であるがゆえに完全であるようにも思えてくるのだ。
*
村上春樹という僕たちの父はいつからか嘘をつくのをやめた。——ハートフィールドだとか、牧村拓だとかいった類の軽いものだ。
そしてその代わり、おそらくあらゆる父親が眠りにつく前の子どもに熊やら蜂蜜やらの作り話をするのと同じように、村上春樹という作家は世界中の人々に物語という大きな嘘をつくようになったのだろう。
それは一見何度も何度も同じモチーフを繰り返しているだけに見えるかもしれない。それにうんざりした人々はこう言うかもしれない。
「またいつもと同じか」
しかしながら——彼をかばうつもりはないが、一息子として一つの見解を述べておこう。
反復こそが物語の本質なのだ。あらゆる神話や昔話がそうであるように。
*
ところで村上春樹が長らく語らず、そこに欠如していたものは本当に「父」だろうか?
日本の小説にあるベタッとした感触、文壇的なしがらみ、嫉妬、葛藤、他者への甘えや依存……。
それから村上春樹に対して未だに根強くありつづける集団的憎悪。
河合隼雄の著作には『母性社会 日本の病理』という日本人論があるが、そういえば、村上春樹の最新短編集の題は『女のいない男たち』だった。
もし仮に——まあそんなことはないとは思うがもし仮に——村上春樹が本当に欠如させたいものを隠すために「父の欠如」を演出していただけだとしたら?
僕たちは長い時間をかけて父の嘘に騙されていただけなのかもしれない。
【引用文献・参考文献】
村上春樹『村上春樹全作品1979~1989①~⑧』講談社、一九九三年
同右『村上春樹全作品1990~2000①~⑦』講談社、二〇〇四年
同右『海辺のカフカ』新潮社、二〇〇二年
同右『アフターダーク』講談社、二〇〇四年
同右『東京奇譚集』新潮社、二〇〇五年
同右『1Q84 BOOK1』新潮社、二〇〇九年
同右『1Q84 BOOK2』新潮社、二〇〇九年
同右『1Q84 BOOK3』新潮社、二〇一〇年
同右『雑文集』新潮社、二〇一一年
同右『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』文藝春秋、二〇一三年
同右『女のいない男たち』文藝春秋、二〇一四年
同右『騎士団長殺し』新潮社、二〇一七年
同右『若い読者のための短編小説案内』文藝春秋、一九九七年
同右『走ることについて語るときに僕の語ること』文藝春秋、二〇〇七年
同右『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』文藝春秋、二〇一〇年
同右『職業としての小説家』スイッチ・パブリッシング、二〇一五年
村上春樹、村上龍『ウォーク・ドント・ラン』講談社、一九八一年
河合隼雄、村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』新潮社、一九九八年
小澤征爾、村上春樹『小澤征爾さんと、音楽について話をする』新潮社、二〇一四年
川上未映子、村上春樹『みみずくは黄昏に飛びたつ』新潮社、二〇一七年
加藤典洋『村上春樹イエローページ1』幻冬社、二〇〇六年
同右『村上春樹イエローページ2』幻冬社、二〇〇六年
同右『村上春樹イエローページ3』幻冬社、二〇〇九年
柄谷行人「村上春樹の『風景』――『1973年のピンボール』」『終焉をめぐって』講談社学術文庫、一九九五年
河合隼雄ほか「現代の物語とは何か」『こころの声を聴く ー河合隼雄対話集ー』新潮社、一九九五年
河合俊雄『村上春樹の「物語」 夢テキストとして読み解く』新潮社、二〇一一年
阿部公彦「村上春樹とカウンセリング」『幼さという戦略』朝日新聞出版、二〇一五年
近藤裕子『臨床文学論 川端康成から吉本ばななまで』彩流社、二〇〇三年
岩宮恵子『増補 思春期をめぐる冒険 心理療法と村上春樹の世界』創元社、二〇一六年
浅利文子『村上春樹 物語の力』翰林書房、二〇一三年
柴田元幸『代表質問 16のインタビュー』朝日新聞出版、二〇一三年
柴田元幸編・訳『ナイン・インタビューズ 柴田元幸と9人の作家たち』株式会社アルク、二〇〇四年
内田樹『村上春樹にご用心』アルテスパブリッシング、二〇〇七年
内田樹『もういちど村上春樹にご用心』文藝春秋、二〇一四年
宮脇俊文『村上春樹を読む。全小説と作品キーワード』イーストプレス、二〇一〇年
小山鉄郎『村上春樹を読みつくす』講談社、二〇一〇年
「特集 村上春樹ロングインタビュー」『考える人』新潮社、二〇一〇年夏号
「魂のソフト・ランディングのために–21世紀の「物語」の役割」『ユリイカ』青土社、二〇一一年一月臨時増刊号