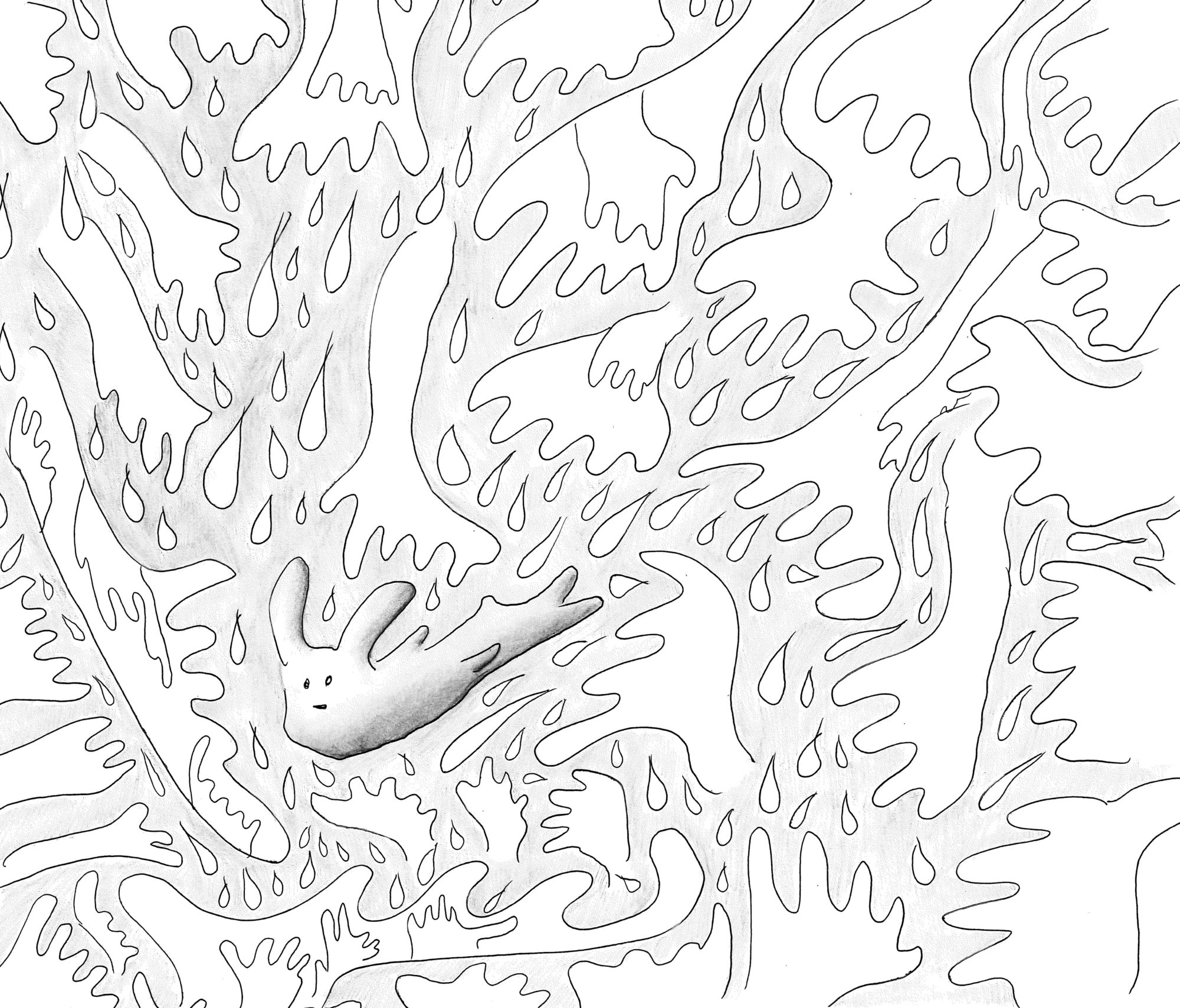自分にとって大切な、かけがえのない人であるはずなのに、その人の寝顔を眺めながら、「どうかこのまま死んで欲しい」と願ってしまう。介護というものが人々にとって等しく辛いものであるのは、物理的や肉体的な負担と同じくらい、自分の心の奥底に渦巻く黒い感情と向き合うことを余儀なくさせられる精神的な負担も大きいからなのだろう。すっかり無力になってしまった姿、ぼけて別人になってしまった姿を見るたびに、かつての元気な姿を、かつてそこにあったはずの存在を、わたしたちは否応なしに想起してしまう。こんな姿を見るくらいならこのまま死んでくれたほうがいいと、ふと思ってしまってから、そんな風に思ってしまった自分のことを恥ずかしく感じる。あれだけお世話になったのに、自分を育ててくれた人なのに、安易に死を願うなんて自分はなんと恩知らずなのだろう、と。そして何も感じないように心の彩度を下げてから、その人が息をしているのを確認して、色彩を欠いた繰り返しの生活をまた続ける。
エストニアの田舎町に住む中年女性アンヌは一人で認知症の母の世話をしている。アンヌの介護を支えるものはいない。娘と息子は遠くに住んでおり、12年前に離婚した元夫は酒飲みで未だにアンヌにつきまとい、彼女も彼を見殺しにはできず縁が切れないでいる。
母の誕生日の夜、街でケーキを買ってきたアンヌはバスから降りたところで元夫に絡まれる。酔っ払って雪の積もった車道に寝転がってしまった彼を立たせ、腕を組んで支えて家に連れていったところが、玄関で無理やり犯されそうになる。なんとか彼を払いのけて階段をかけ上り部屋に入ろうとするものの、騒動に怯えてしまった母はドアに鍵をかけてアンヌを入れてくれない。怖がる母は目に涙をためて言う。「あんたは誰? 私の娘はティーナよ」。ろくでなしと結婚してしまったアンヌに失望した母は彼女をもはや娘として覚えていないのだ。そんな母をアンヌは優しく説得し、「ケーキを焼くわ」と抱きしめる。これが彼女の日常だ。疲れ切って感情を抑圧しているアンヌの顔は人生を諦めているかのように無表情で、実用一辺倒のくすんだ色の服が彼女をより老けさせている。
ある夜、母の傍らで寝ていたアンヌは水を飲みにキッチンに立ったが、戻って母の寝息を確かめると呼吸していないことに気づく。母の手が硬くなっているのを確認し、ベッドに座り込んだアンヌの顔には、悲しみの表情も安堵の表情もはっきりとは読み取ることができない。
母の葬儀の後、がらんどうのようになっていたアンヌの元に、以前所属していた介護の職場から仕事の依頼が舞い込む。パリに住むエストニア出身の老婦人の世話係だ。娘に電話して相談し、ぜひ引き受けるべきだと言われたアンヌは、重い記憶を捨てていくかのようにスーツケースに必要な荷物だけをまとめてパリに旅立つ。ささやかな期待を胸に夜の空港に降り立ったアンヌだが、雇い主である中年紳士ステファンと合流して車に乗るとそんな明るい気持ちもすぐにしぼんでしまう。パリに来るのが夢で学生時代には熱心にフランス語を学んだとアンヌが語っても、ステファンは考え事をしているようでろくに聞いていないからだ。アンヌは口をつぐみ、暗い窓の外を眺める。高級アパルトマンに着くとステファンは簡単に仕事の説明をし、寝室で寝ている老婦人に聞こえないようにアンヌにそっと告げる。老婦人のフリーダは「辛辣な皮肉屋」だが、振り回されないように、と。
アンヌはステファンのそのセリフの意味をすぐに知ることになる。フリーダはただの「病弱で孤独なエストニア女」ではなく、母語であるエストニア語を決して話さない誇り高きパリジェンヌなのだ。朝食にスーパーで買ってきたクロワッサンを見て「プラスチックを食べろと?」と嫌味を言われ、お茶をわざとこぼされ、「家政婦なんかいらない」とさっそく解雇を言い渡されるアンヌ。困った彼女はすぐ近くでカフェを経営しているステファンの元へ行って助けを求めるが、今まですでに何人もの家政婦が同じ目に遭っているのを見ている彼は必死にアンヌを説得する。彼はフリーダの家へアンヌを再び連れて帰る。ステファンの姿を見たフリーダは表情を変え、彼に甘えて腕を組み、家政婦ではなくてステファンに面倒を見てもらいたいと駄々をこねる。アンヌはフリーダの態度を見て、それまで彼らを親子のような間柄と思っていたがどうやら違うらしいことに感づく。案の定、ステファンに訊ねれば、彼はフリーダのかつての愛人なのだという。フリーダはエストニア出身だが人生のほとんどをパリで過ごしていて故郷には縁がなく、夫亡きあとも裕福な暮らしをしてはいるものの、子供もおらず天涯孤独の身なのだ。わがままで気まぐれなフリーダには友達もおらず、カフェの仕事で忙しいステファン自身も今ではフリーダをもてあましており、かといって以前睡眠薬を飲んで自殺を図られたことがあったのでほっとくわけにもいかず、家政婦としてアンヌが雇われた。今や彼女にはステファンとアンヌしかいない、というわけだ。
一度は国に帰ろうとしたアンヌだが、ステファンの再三の説得を断れず、また、故郷に帰るのも嫌だったのだろう。アンヌは辛抱強くフリーダの要求に応じ、次第に信頼を得るようになる。そしてフリーダというパリに住む一人のエストニア人女性の生き方を知ろうとし、彼女の語る昔の男たちの話に耳を傾け、夜になるとこっそり書斎の写真や新聞記事の切り抜きを見て彼女の過去を想像する。たしかにフリーダは辛辣な皮肉屋ではあるが、まだ若い頃たった一人でパリにやってきて生き抜いた自由な価値観を持った女性なのだ。フリーダの生き様は年齢にもエストニアの伝統にも縛られていない。いくつになっても自分が女性であることを忘れず、来客がなくても化粧をしてシャネルのスーツに袖を通し、ベッドに寝る時は片側に寄って隣に男のためのスペースを空けておき、暇な時間には必ず本を読む。アンヌはそうした自分のスタイルを確立しているフリーダの生活や、毎晩仕事が終わったあと密かに楽しんでいた夜のパリのウィンドウショッピングから、今まで知ることのなかった新しい空気を徐々に肌に吸収していく。
一方、アンヌが故郷で母を亡くしたばかりだということを聞いたフリーダも、孤独なアンヌにかつての自分の姿を重ねたのか、少しずつではあるがアンヌに心を開き、自分を大事にする生き方を教える。出かけることなく家の中に引きこもって寝る時も自分の体を自分で抱きしめるように強く腕を組んでいたフリーダの心は、アンヌの存在によって次第にほぐれてゆき、二人の関係性はお互いにドアの隙間から相手を盗み見るようなよそよそしいものから、向かい合いで座って爪にマニキュアを塗ってあげる/もらうような距離に近づいていく。
ある日フリーダは、まだパリ見物をしていないというアンヌに、二人でおしゃれをしてステファンのカフェに行こうと提案する。フリーダにとっては久々の外出だ。アンヌはどれにしようかとベッドに服を並べて、赤いトップスを選び、鏡を見ながら口紅を塗る。フリーダはアンヌの仕上がりをチェックし、普段着のダウンではなく自分のバーバリーのトレンチコートを着せて、グリーンのストールを後ろ向きに巻いてやる。パリの晴れた街並みを二人で腕を組んで女子学生のように服やセックスの話をしながら歩くシーンは、冒頭のエストニアでアンヌが酔いつぶれた元夫の腕を持って雪道を歩いていたシーンとまるで対極にあり、「とてもきれいよ」とフリーダに褒められたアンヌの顔には笑顔がこぼれている。
ところが、アンヌとフリーダの良好になった関係性を図らずも壊してしまうのは意外なことにステファンだ。ステファンのカフェに到着した二人は当然大いに歓迎されるのを期待していたが、彼は紳士的に対応するものの「僕にも人生がある。悪いが、君を中心には回らない」とフリーダに告げてさっさと店の奥に戻ってしまう。ステファンにとってフリーダは、かけがえのない存在であると同時に疎ましくもある「早く死んで欲しい」存在なのだ。ショックを受けて帰ったフリーダは寝込んで食べることもやめてしまい、心配したアンヌはステファンに「あなたにとって彼女は死人なのね」と言って怒る。それは彼女がかつて自分の母に対し密かに抱いていた感情であるが、そう思うことを自分に対して禁じていた彼女はステファンのあからさまな態度を受け入れられない。ステファンは言う。「確かに彼女を愛したし、カフェも持たせてもらった。だが、店のせいで一生束縛されなきゃならないのか?」
落ち込んだフリーダを励まそうとアンヌは一人思案して、フリーダのかつての友人であるパリに住むエストニア人たちを家に連れてくるが、アンヌのせっかくの努力は裏目に出てしまう。フリーダは彼らを招かれざる客だと言い、友人たちも「50年前、妻のいる男と寝ただけ」のフリーダを「エストニアの魂を失った」と批判する。逆上したフリーダは客人たちを追い返し、アンヌに対しても余計なお節介をしたと怒り、「どうせあんたは一生、エストニアの田舎者よ」「母親の代役はごめんよ」と毒舌を撒き散らす。言われたアンヌも堪忍袋の尾が切れ、「あなたがこんなに孤独なのは自分のせいよ。死にたいなら窓から飛び降りれば?」と捨て台詞をはき、荷物をまとめてフリーダの家を出ていく。
アパルトマンを飛び出てアンヌが向かったのはステファンの元だった。彼はカフェの2階の個室にいて、アンヌはノックをして彼の部屋に入っていく。ネクタイを外して休んでいたステファンは彼女を優しく招き入れて言う。「この間、君の言ったことは正しい。僕は彼女の死を待ってる」。アンヌは答える。「分かるわ。私も母の死を待ってた」。大切な人の死を望むという、心の奥底にしまってなるべく見ないようにしていた感情を二人は告白し合い、互いの重荷を理解し、そうすることによって自分を許し合う。言葉を発するごとに距離が縮まり、背景に映る窓枠の中に二人の姿が小さく収まって、柔らかで親密な光が二人をまるごと許すように包むこの場面は、作品を通して最も優しい瞬間だ。
よく見ていると、さりげなくステファンはたびたび隠れて酒を口にしているのだが、彼はわたしたちにアンヌの酒乱の元夫を彷彿とさせる存在でありながら、両者は確実に違う存在であることがここで強調される。待っててと言ったにもかかわらず元夫に無理やりドアを押し開けられたエストニアでのシーンに対し、ここではアンヌからステファンの部屋に赴いて招き入れられ、部屋に入ってもアンヌが自分でドアを閉める。アンヌの意思を無視して思い通りにしようとしていた元夫の姿は、今ではアンヌを一人の独立した女性として尊重するステファンによって置き換えられているのであり、そしてアンヌ自身ももう、娘に電話する癖からいつのまにか脱し、フリーダの暴言にもはっきり言い返すことで自分自身を粗末に扱わず、他人にも粗末に扱わせない女性と変化しているのだ。
それまでは随所でアンヌが乗り物に乗っている姿が映されていた。冒頭のバスに揺られながら窓の外の景色を虚ろに眺める姿からはじまり、パリに着いて飛行機から意気揚々と降りたったにも関わらずその後すぐステファンの運転する車の助手席で気まずそうに黙ってしまう姿、フリーダに家を追い出されてパリを散歩している最中に乗った地下鉄でうっかり降り損ねてしまった姿。バスでも車でも地下鉄でも、アンヌはなんとなく心細そうな、居心地悪そうな表情を浮かべていて、その姿はどこにいても彼女が異邦人でしかないかのような、自分の家ですら鍵をかけて締め出されてしまって、どこにもあたたかく受け入れてもらえる場所のない、いつも他人に振り回されてきた彼女の人生そのものを表しているかのようだった。
ステファンの部屋を出たあとに映されるのは、行き先の決まった乗り物に不安げに揺られているところではなく、アンヌが自分の足で歩いている姿だ。膝の見えるワンピースを着て、ストラップのついた高いヒールの靴のままスーツケースを片手にパリの街を颯爽と歩く彼女は、すれ違う男性が振り返るほど魅力的で、いくら彼女が「国へ帰る」つもりでいても、いまや彼女の存在はすっかりパリに馴染んでしまっていることが見ているわたしたちにとって明らかだ。しかしだからといってアンヌは第二のフリーダとなっているのではない。パリ見物の途中でアンヌは、以前フリーダに褒められたヒールの靴を脱いで、エストニアから持ってきたブーツに履き替え、黒いコートの上にいつものフード付きダウンを着て、エッフェル塔を見上げながら熱々のクロワッサンを頬張る。フリーダにパリの影響を与えてもらいながらも、アンナはエストニア人としての自分を保ち続けている。それは同じ金髪の移民であると同時に、エストニアを否定するフリーダとはまた違った、アンヌならではの「パリのエストニア人女性」としての生き方だ。
一晩パリの街を満喫したアンヌはフリーダの元へ最後の挨拶をしにいく。アンヌを失ってしまったのではないかと落ち込んでいたフリーダは、彼女が戻ってきたものだと安堵し、当初は「ここは私の家」と言い張っていた自分のアパルトマンに「ここはあなたの家よ」と言って迎え入れる。そこには感動のキスもハグもない。ただドアを開けて、名前を呼んで、優しく部屋に受け入れるだけだ。アンヌは帰ってきたわけじゃないと言おうとして、奥の部屋へと戻っていくフリーダの後ろ姿をじっと見つめて、改めて、自分が本当はどこにいたいのかを悟る。
まだアンヌがパリにやってきたばかりの頃、以前自殺未遂をしたのはステファンが原因かとフリーダに直接訊ねる場面がある。彼がこんなに尽くしているのはあなたを愛しているからなのに、と。それに対し、フリーダは「そんなに単純じゃないの」とだけ答える。この映画ではフリーダの死んだ夫のことも故郷の母や兄のことも、アンヌの姉妹や二人の子供のことも、ステファンの元恋人のことも、一瞬だけ語られることはあっても詳しく説明されることはない。わたしたちはどれだけ言葉を費やしたところで他人の人生や内面を完璧に知ることなど不可能で、わたしたちにできることといえば、その人の写真や私物を見て勝手に過去を想像することくらいのものだ。だがそれほど複雑で、決して理解しえないからこそ、わたしたちはある人の一部分を憎みながら、ある部分を愛するということが可能になる。その人の死を願ってしまうほど疎ましく思うと同時に、その人を愛おしく思うことは必ずしも矛盾しない。
アンヌがフリーダの元に戻ってきたからといって根本的には何一つ解決してなどいない。きっとフリーダは死ぬまでわがままな「怪物」であり続け、アンヌとステファンは怪物の寝息を確かめ続けるのだろう。けれども朝食をいつもの決まりきったものからまったく新しいメニューに変えてみたり、あるいはちょっと近くのカフェに行くのに、いつも着ていたコートを脱いでそれまで着てみたことのないダウンに腕を通してみたりするだけで、わたしたちは諦めに満ちた日常をわずかに彩ることができる。自分を許すとは、そんなささやかな逸脱からはじまるのだ。