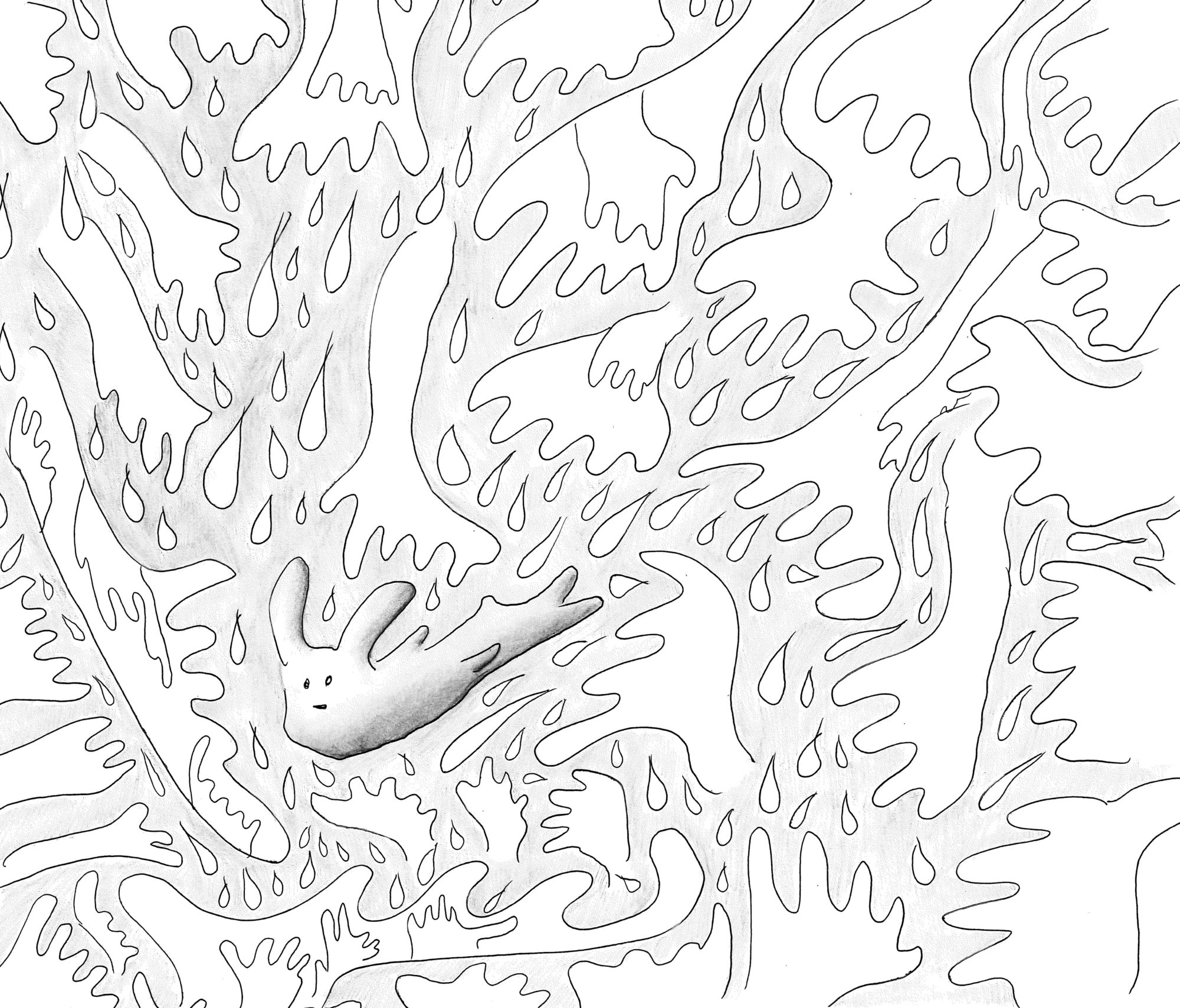晩ご飯をあげたら忙しい
わたしが戸締りしているとメイは
はやくはやく、といってくるから
ちょっと待って、といって
コートを着る
ここのところだいぶ日が長くなってきたから
手袋とマフラーは必要ないみたい
置きに戻ってから鍵を閉める
玄関の段差をおりるとメイは
リードを噛んで引っ張って頭を振りまくる
通りを掃除していたお肉屋さんのおばさんが元気ねぇと笑う
前に黒い雑種を飼っていたけれど油粕を食べて死んでしまったらしい
公園まで走って競争
どうやら今日は悪い方の爺はいなさそうだ
メイが草むらでおしっこをする
トイプードルのトリオがいなくなってからリードを離して
わたしたちはわたしたちだけの鬼ごっこをする
茶と白と黒の長い毛がとび跳ねる
でもすぐにメイの注意はそれて
ベンチのまわりに散らばっているポテトチップスを漁りはじめるから
捕まえてリードをつけて
公園の外に引っ張っていく
右手では太陽が傾いて
雲が淡いピンクに色づいている
チワワのおじさんと近況報告し
新興住宅が並ぶ閑静な通り
なぜかいつもメイはここの車道の真ん中の線を歩きたがる
だめだってそこは、といっても
ここじゃなきゃやだ、というから
まあ誰もいないしいいか、とわたしたちは真ん中をゆく
まもなく車の音が聞こえてきて
わたしが歩道に戻ろうとすると
メイがうんこをしようとするから
急いで脇へ引っ張っていく
黒のベンツが唸って走り過ぎる
わたしがまだ幼稚園の頃から
しぶとく残っている畑の脇を
もくもくと歩く
空の比重が少しずつ
赤から青へと変わっていく
わたしがこの街に戻ってきた数年前は
メイは肥満で大の散歩嫌いで
五分も歩いたら車道に寝転がって抵抗していた
わたしもこの街や人やこの街にこびりついた記憶が嫌いで
日が沈んでからしか散歩には行かなかった
でもいまやメイは標準体重となって
自ら散歩をねだるようになり
わたしも嫌なものからできるだけ逃れる技を覚えた
前までメイは
知ってる道しか歩こうとしなかったけど
だんだん知らない道を進んでいくようになった
前までわたしは
片耳にイアホンをして英語を聴きながら歩いてたけど
最近それをやめてみて
この街で見ても空はきれいなんだということに気づいた
夕陽が落ちていく交差点
三階建てのマンションがオレンジ色に染まり
良い子のチャイムが流れる
小学生の頃じゅんちゃんと一緒に
よくいたずらして怒られてた市民センターの前を過ぎ
青信号
爆音のバイクを追いかけようとするメイを制し
道を曲がる
新聞屋さんが一日の終わりの作業をしている
大小さまざまの植木の並べられた
良いお爺さん家のとなり
猫のたまり場になってるアパート
わたしは毎日しゃがんで声をかけるのだけど
メイがいるからみんななかなか近づいてくれない
軽トラの下にいる三毛猫に向かって
わたしがゆっくり瞬きしていると
メイは甲高い声で文句をいう
わたしは名残惜しくて何度も振り返る
メイがわたしを引っ張っていく
遅くなった足取り
家の前にきたから
なかに入ろうとするがメイは頑なに動かない
しょうがないから
のろのろと
公園に戻る
サッカーをしている子たち
きっとあきらくんたちだろう
昔はメイも混ぜて遊んでもらってたのだけれど
彼らの学年が上がるにつれて混ぜてもらえる時間も減っていって
彼らが中学校に入ってからは
メイは端っこで見ているだけになっていった
向こうのブランコにまたがった女の子たちが笑い転げている
伏せをしたメイのお尻がわたしのふくらはぎに当たる
あたたかな呼吸
雲が静かに流れ
電線を通り抜けてゆく
電柱がなければもっときれいなのにと思うけど
でも空にたわんだ黒い線が架かるのも
案外悪くないのかもしれない
街が濃い青色に沈んでゆく
あの色はなんという名前なんだろう
きっと昨日とはまた違う色
記憶に留めておきたくてわたしはじっと見つめる
どこからか玉ねぎを炒めるにおい
いつまでもボールを目で追っているから
そろそろ帰ろっか、という
どちらともなく立ち上がる
メイが玄関の段差をのぼっていく
わたしもそのあとをのぼっていく