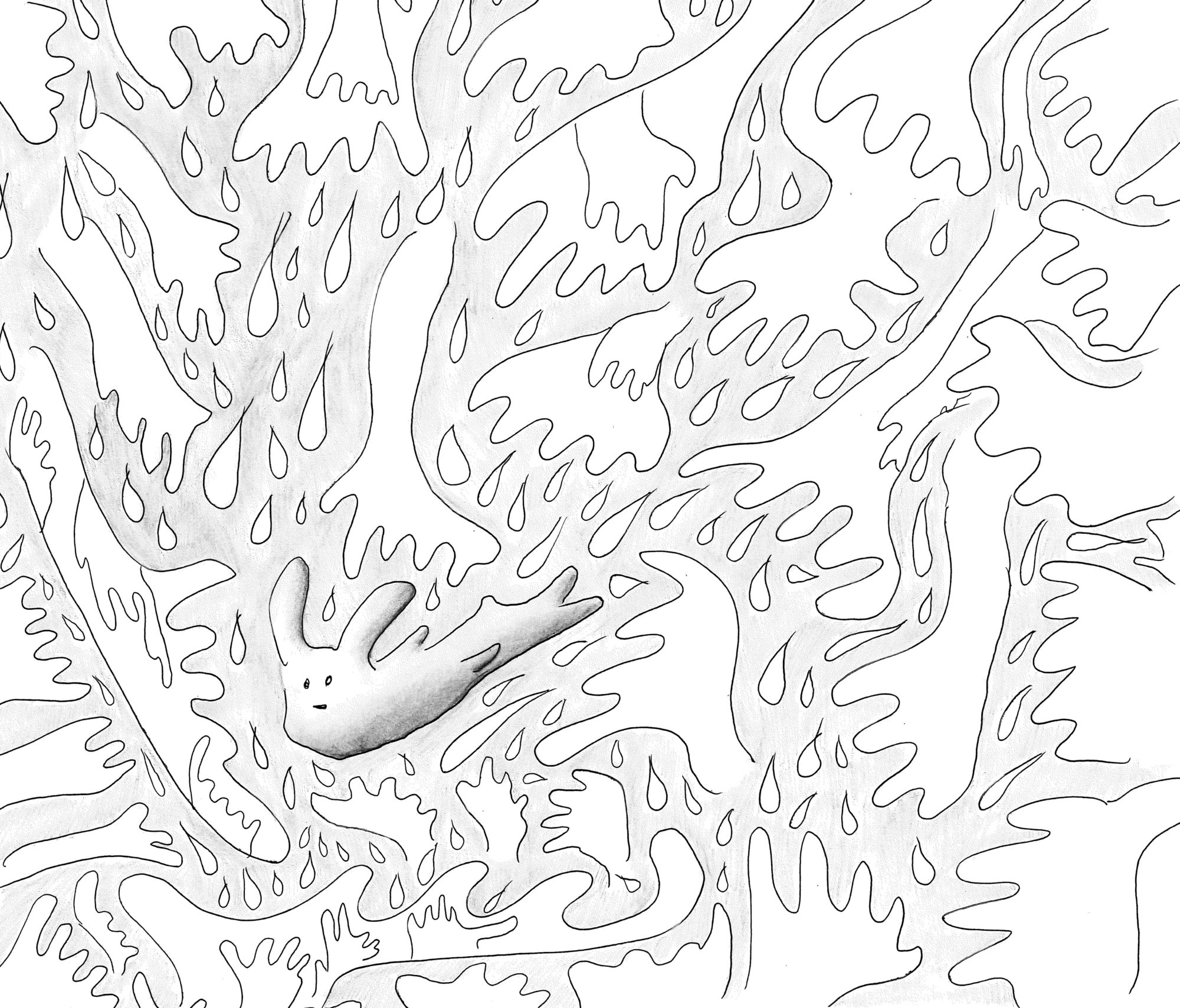5月25日発行予定の『生活の批評誌no.5』(特集:「そのまま書く」のよりよいこじらせ方)に、「教室のうしろの席から」というエッセイを寄稿しました。

5月29日(日)の文学フリマ東京にて初頒布されます。(ブース番号は【テ-11】)
その後、全国の個人書店などでも取り扱われる予定です。(生活の批評誌twitterアカウント @seikatsuhihyou にてお知らせ)
目次など、内容の詳細はこちらをご参照ください。
*
わたしは在学していた大学院でセクハラの被害に遭い、2019年から加害者・大学と裁判をしつつ、2020年の秋に「大学のハラスメントを看過しない会」という団体を立ち上げ、「原告A」として活動していましたが、昨年末から時間をかけて上記のエッセイを書いていく過程で、今回、名前を出すことに決めました。
エッセイの中で詳しく書きましたが、長い間わたしは自分が「被害者」だと認めることを拒んでいました。それは、自分が劣位に置かれていることを認めたくないという悔しさがあったからでもあります。普段、「自立した女」であろうとしている自分の弱さを、人前にさらすような恥ずかしさがあったからでもあります。
「被害者」とはいったい何なのか。運動や裁判をしていくなかでわたしが気づいたのは、「加害者は被害者意識に満ちている」ということでした。加害者たちはわたしの意見や気持ちに耳を傾けることなく、どこまでも自分を正当化し続けます。わたしは彼らと同じ土俵に立って、どちらの方が被害者なのか言い合うような、“低レベル”なことはしたくありませんでした。
だから、運動をはじめた当初、わたしは愚痴や弱音をほとんど吐きませんでした。いろんな人に会いに行って話をし、二次加害にあたる発言をされても、傷ついている自分を見ないようにして、また次の人に会いにいきました。周りから「フットワーク軽いね」「行動力すごいね」と言われることを喜んでいたし、「大変な目にあっても飄々としている自分」に酔っていた部分もあったと思います。
加害者たちのように「むしろ自分は被害者なんだ」と周囲に触れ回っている暇があったら、そのあいだにわたしは、彼らが目を向けないようなところまで視線を配り、なるべくたくさんのものたちに手を差し伸べようと思いました。そうしてハラスメントとはまったく別の人権運動や、動物のための工場畜産反対の運動にも深く関わりました。それは、「文学」への失望の反動でもあったと思いますが、そうやって次元をずらすことで、視野のせまい彼らのことを、高みへ至ったわたしは見下ろしていると感じたかったのだと思います。「わたしよりもっと大変な目にあっている存在はたくさんいるのだ」と自分に言い聞かせ、毎日あちこちへと走り回ることで、わたしは自分自身の傷と向き合うという作業をあとまわしにしていました。
そうやって日々、他の運動にも参加するなかで、わたしはハラスメントの運動をやる際にも、あくまで自分のことを「当事者」といい、「被害者」という呼び名を使わないよう気をつけていました。
また、以前のわたしはフェミニズムの議論を聞くたびに、「いまどき女とか男とかどうでもよくない?」と冷ややかに聞き流していました。わたしは性自認があやふやで、一応自分を「女」と認めてはいるものの、性別なんか別にどうでもいいと思っていました。小さい頃から母や祖母に、女であるというだけで兄と区別され、どこかにでかけてもわたしだけ迎えにこられたり、外泊を禁止されることにうんざりしていました。しょっちゅう痴漢を心配されたり、露出を気にされることにうんざりしていました。大学のときに一人で海外に旅行にいくことになったときには、禁止されることはなかったものの、「レイプされそうになったときは相手にこれを渡しなさい」と祖母からコンドームを渡されました。そういうことのすべてにうんざりしていました。
わたしは「被害者」が嫌いでした。
2019年のはじめ、活動の一貫で、大学におけるハラスメントの男性被害者たちと顔を合わせることとなりました。わたしの当時の協力者は、遅刻癖のひどい男で、わたしとの打ち合わせのときには当たり前のように遅刻したりそのまますっぽかしたりしていましたが、珍しくその日は5分前に来ていました。彼にとって、今日会う男性被害者たちよりもわたしは雑に扱っていい相手だったのかと思うと少しイラッとしました。それから双方、簡単に自己紹介しあい、本題に入りました。互いの情報交換をする場になるとわたしは思っていたのですが、彼らは自分たちの話を主にしていて、あまりこちらの話を聞きたいという様子はありませんでした。わたしたちは彼らの話に耳を傾けました。途中、加害者の描写がおかしくてわたしが笑ったら、協力者から「彼らは被害者なんだからさ」とたしなめられました。普段わたしには気を遣わないわりに彼らに対してはやけに細やかに気を遣うんだなと引っかかりましたが、内輪で揉めてもしょうがないので、「わたしも一応被害者なんですけど?」という言葉は胸にしまいました。
ひととおり話を聞き終わると、わたしの協力者は「彼らのために慰労会をやろう」と提案し、そのままみんなで居酒屋にいきました。わたしは協力者からも誰からも一度も「慰労会」などしてもらったことはなかったので、いったいなんでわたしが彼らを「慰労」しなきゃいけないんだ?と内心ムカつきましたが、表には出さず振舞いました。彼らは初対面のわたしにも隠すことなく弱音を吐き出していました。会計は年上のわたしたちが多く出すことになりました。わたしは金もないしケチなのであまり気が進みませんでしたが、ここで嫌がっても大人気ないと思い、表情を変えずにお金を出しました。
みんなと別れ、最終の電車で最寄駅に着くと雨が降っていて、いつもなら自転車で帰る家までの道を、とぼとぼ歩いて帰りました。深夜1時過ぎ、人通りはまったくありませんでした。わたしはヒールのブーツを履いていて、爪先が雨に濡れて冷えました。なんだか悲しい気分だったので、ヘッドホンをして音楽を聴きました。5分ほど無人の大通りを歩いていくと、左側のフェンスの前に男が立っていてぎょっとしました。立ちションをしているようだったので、急いで目を逸らしましたが、一瞬目が合ってしまい、まずいなと思いました。男はわたしの方へ歩いてきました。傘のなかをのぞきこんできました。男は小柄で、端正な顔をしており、ジャージを着ていました。男はわたしに何か話しかけてきているようでしたが、わたしはヘッドホンを外さず聞こえないフリをしました。男はそのままついてきました。ナンパだったら無視していればそのうちついてこなくなります。でも男はわたしの肩に手を回してきました。これはやばい、と思いました。ヘッドホンを外すと、「ちょっとだけでいいから」という声が聞こえました。見ると男は下半身を出していました。わたしは腕を払いのけ走りだしました。
一番近くにあった建物の自動ドアを拳で叩きました。不動産屋のようでした。電気はついておらず、誰もいないようでした。ガラスを叩いて割ったら防犯アラームが鳴って誰か気づくかもしれないなどと考えていると、視界の端で男が反対側の小道に走って逃げるのが見えました。とにかく人のいるところへいかなきゃ。わたしはコンビニへ向かいました。傘もささず、走ってよろけながら、スマホで警察に電話をかけました。
コンビニのなかで、あがった息を抑えていると、まもなく警察がやってきました。最近、似たような被害が相次いでいて、ちょうどパトロールしていたところだったそうです。聞き取りは詳細になされました。終始丁寧な対応でした。車で家まで送ってもらいました。でも、最終的な解決策は、「女の子がこんな遅い時間に歩いていちゃだめだよ」「ヘッドホンをして歩いちゃ危ないよ」というものでした。
わたしはそのとき、その男に対しても警察に対しても協力者に対しても腹が立ちましたが、でも何より、他の「被害者」を憎みました。平気で人前で弱音を吐けることが羨ましかった。他にも仲間がいるのに、協力してくれている教員もいるのに、いったいこれ以上なんの不満があるんだろう?と思いました。彼らは男だから、その日わたしがあったような目にあうこともあまりないでしょう。今頃わたしがこんな目にあっているなどと想像もしてないでしょう。わたしは口では「いまどき女とか男とか関係なくない?」と言いながらも、男であるという特権を持っているにもかかわらず弱さをさらけ出せる彼らに嫉妬しました。ヒールの靴で、爪先立ちで、かろうじてバランスを保っているこのわたしに、弱音を吐いてくる彼らが許し難かった。
それから約一年間、わたしはハラスメントの運動をやめ、それに関わる人間関係を断ちました。
*
現在、わたしは別の協力者たちに支えられながら、基本的に一人で団体を運営しています。普段は各々活動していて、必要なときに助けを呼びかけ、ときどき手伝ってもらうという形をとっています。彼女たち/彼らは遅刻もすっぽかしもしないし、連絡を無視もしないし、互いに意見を聞き合うし、何よりわたしが「被害者」であるということを理解してくれています。
そのおかげで、わたしは以前より、愚痴も弱音も気軽に吐けるようになりました。そうすることによって、他の被害者が愚痴を吐いていても腹が立たなくなったし、お互い支え合っていきましょうと協力しあえるようになりました。人が弱さをさらけ出しているのを見ると、わたしも出していいんだな、と思えるようになりました。そうやって、少しずつ、「被害者」という存在の仕方を許せるようになり、自分自身も「被害者」であるという事実を受け入れられるようになってきました。
とはいえ、「わたしの方が大変な目にあってるんだけど」とか「それをわたしに言うか?」という気持ちがまったくないかといえば、嘘になります。でも、そういう気持ちが出てきたときは、「ああ、今わたしは羨ましく思ってるんだな」と自分の感情になるべく早く気づけるようになってはきています。そういう感情が出てくるときは、大抵「無理をしすぎ」のサインなので、その場から離れたり、負担を減らすようにしています。
「被害者である」と名乗ることには危険性がともなうと思います。「被害者vs加害者」という単純な二元論に陥ってしまうのではないかという不安もあります。それでも、まずは被害者として自分を認め、自分の中の痛みを引き受けること、それなしには前に進むことはできないと思うのです。だからわたしは今では「被害者」であると、ちゃんと名乗るようにしています。
よく、「もっと強くなれたらいいのにな」と思います。何が起こっても、誰に何を言われても、動じないだけのメンタルがほしい。ときどき、変わることのない加害者たちが羨ましくなることもあります。いちいち取り乱してしまう自分、感情があふれてしまう自分に嫌気がさすこともあります。
でも、自分自身に泣くことを許していない人は、他人が泣くことを許せないから。自分自身が弱音を吐くことを受け入れらない人は、他人が弱音を吐くのも許せないから。
わたしはわたしのすべての感情を受け入れていきたいと思っています。
*
去る3月、わたしは自分にとって娘のような存在であった犬を失いました。突然死でした。持病があったため去年から闘病し、病院に通い続けていましたが、持病とは関係なく、おそらく脳の問題で、何の前触れもなく亡くなりました。10歳2ヶ月でした。
その日、わたしは犬とリビングのカーペットに寝転んで昼寝をしていました。あたたかくなりかけてきた3月の日曜日の気持ちの良い午後でした。家族が外から帰ってきて、犬はいつものように出迎えるために立ち上がり、廊下を軽い足取りで歩いていきました。30センチほど開けてあるドアの隙間を、ひょいとくぐりぬけていくのがお決まりだったのですが、大きなお尻がひっかからないかわたしは毎回心配で、ちゃんと通れたか見届けていたものでした。
そろそろ散歩の時間かと思いつつも、起き上がる気になれずにごろごろしていると、家族がわたしの名前を呼びました。いったい何だろうと玄関に見に行くと、犬が倒れていました。失禁していました。わたしは悲鳴をあげ、駆け寄りました。動いていませんでした。わたしは急いで動物病院に電話をしました。すぐにきてくださいと言われました。わたしたちはいったん犬を廊下に移し、急いで支度しました。持ち上げた時、犬の体はぐにゃりとして、力が入っていませんでした。犬の胸に手を当てましたが、動いていませんでした。口の前に手を当てても、呼吸をしていませんでした。でも、わたしは彼女がもう死んでいるかもしれないという疑問を口に出してしまったら、本当にそうなってしまうような気がして、前足を握りながら、大丈夫だよ、と呼びかけました。すでに足は冷たくなっていました。
わたしと家族は犬を車に乗せ、ボンネットとリアに初心者マークを貼り、急いでキーを回しました。わたしは犬をつれて旅行にいきたくて、去年免許をとったばかりでした。後ろの席で家族は、犬を抱き抱えながら、彼女に聞かせるように歌を歌っていました。赤信号になるたびに、わたしは振り返って犬の足を握りました。大丈夫だよ、と語りかけました。でもその肉球は触るごとに冷たく固くなっていくようでした。
動物病院の駐車場に車を止め、座席から降り、横たわる犬を抱きかかえようとしましたが、わたしも家族も手足が震えてしまって、14キロある彼女の体を持ち上げることができませんでした。わたしは病院に駆け込み、受付の方に状況を伝えようとしましたが、涙が出てくるばかりで、何と言ったらいいのかわかりませんでした。わたしの口からやっと出てきた言葉は、「生きてるかわからない」でした。急いで看護師の方が出てきて、車まできて、犬を抱き抱えて、走って病院に運びこみました。中では院長やスタッフの方たちがすでに機材の準備をしていて、犬を診察台の上に置くと、チューブをつなぎ、心臓マッサージがはじまりました。クリップが留められた舌は、紫がかった白色になり、だらんと横に垂れていました。院長が犬の心臓を押すたびに、わたしは、動け、動け、と祈りました。今まで当たり前のこととして見過ごしていたけれど、動くということはすごいことなのだと思いました。彼女が呼吸していたのは奇跡みたいなものなんだなと思いました。頼むからもう一度動いて欲しい。涙と鼻水でぐちゃぐちゃになりながら、わたしは彼女の胸を見つめ、心の中で祈り続けました。
10分か15分くらい経ちました。院長がわたしと家族の方にやってきて、たぶんこれ以上続けても戻ることはないけれどどうしますか? といいました。わたしのポケットは右も左も濡れたティッシュでいっぱいでした。わたしは犬のお腹に手を置いて、もう大丈夫です、と告げました。彼女の目は半開きのまま、遠くを見ているようでした。
*
毎朝、わたしは雨戸を開け、歯を磨き、それから祈ります。
線香をあげ、おりんを鳴らし、手を合わせます。
そうやって一日をはじめます。
*
わたしは、これから裁判所に長文の陳述書を提出しなければならないという負担からただでさえ鬱になっていたおりに、突然犬を失ったことによって、自分の魂が半分持っていかれたように力が抜けてしまいました。
彼女の存在なしに、これからの戦いを持ち堪えられる気がしませんでした。
座っている気力もなく、毎日ただ横になっていました。
裁判の作業のために、自分のやりたいことにいつまでも復帰できなくて、すでに費やしてしまった何年もの時間のことを思うと、途方もなく虚しくなりました。
事件から5年もたったのに、加害者たちの主張は何ひとつ変わらず、わたしがしてきたことに意味はあったのだろうかと、わからなくなりました。
いろんな方向から二次加害を受け続けて、言い返す気力もなくなりました。
大学という姿の見えない大きな組織相手に、裁判という戦いを続けていると、自分にはなんの力も価値もないような気がしてきました。
ニュースをみるたびに、とてつもない暴力の存在を目にし、押しつぶされそうになりました。
これまでの人生で、あまりにもいろいろなものを失いすぎて、これからも生き続ける意味はあるんだろうかと、どんどん深みへ迷い込んでいくような気持ちになります。
*
わたしはその問いにいまだ答えを見つけられないでいるけれど、
でも毎日なんとか生きています。
地面を這いつくばって生きています。
心臓が動いている限り、わたしも生き続けなくちゃいけないのだと思っています。
*
おりんの音が鳴り響いている間は、犬と繋がっているような気がします。
一緒に寝転がりながら、彼女に触れていたときの、あたたかくてやわらかな感触を思い出します。
そこにはたしかに「よきもの」があったのだという記憶を思い起こさせてくれます。
わたしはその記憶を絶やさぬよう、なんとか守っていきたいと願っています。
*
今回、わたしにとって、とても重要な文章を書きあげる機会をくださった、『生活の批評誌』編集長の依田那美紀さん、わたしの小さな声を拾い上げてくれて本当にありがとうございました。
それから、いつも力を貸してくださっている川口晴美さんと協力者の方々、たった一人で代理人を引き受けてくださっている山本裕夫弁護士、苦しいときに必ず助けてくれる友人たち、そして日々を支えてくれている家族に、深く感謝します。
+大学のハラスメントを看過しない会 公式HP